雨の飴玉
私の近所には古い駄菓子屋がある。そしてお店と共に年月を過ごしてきた事を思わせるおばあちゃんが店長さんだ。この駄菓子屋は私が小学生の頃からよく通っている。遠足の時のおやつは毎回ここで買った。今でも高校のクラブでお菓子パーティーを開く時なんかにここで買ったものを持っていくと、皆「懐かしい」と言ってくれ好評だ。そんな駄菓子屋にはあるサービスがある。それは雨が降っている時にお菓子を買うと、飴玉をひとつくれるのだ。雨は子供にとって外で遊べない憎らしい天気だが、私にとっては飴玉が貰える楽しみな天気だった。
ある日この駄菓子屋が閉店すると聞いた。おばあちゃんのお孫さんが結婚するのをきっかけに、引っ越して同居する事になったそうなのだ。それはおめでたい事ではあったけど、ずっと行き続けた駄菓子屋がなくなってしまうのは寂しかった。
それは他の常連さんも同じだったようで、駄菓子屋の閉店日におばあちゃんに内緒でお見送り会をする事になった。私は小学生の頃の友達と共に何をしようか考えた。「まず花道は欠かせないよね。」「紙吹雪なんてどうだろう?」「無理だよ、ゴミになっちゃうよ」など様々な意見が飛び交う。しかしどれもしっくり来ない。すると誰かのお腹が鳴ったのが聞こえてきた。そこで皆で駄菓子屋に行く事になった。
駄菓子屋の中にはおばあちゃん以外誰もいなかった。おばあちゃんしかいない店内は何だか薄暗く見えた。おばあちゃんは私達に気付くと優しい声で「いらっしゃい」と迎えてくれた。その声があまりにも普段通りで、急に寂しさを覚えた。気を紛らわすためにもわいわい好きなおやつを選んでいると急に店内が暗くなった。驚いて顔を上げた瞬間、ザァッと入り口の向こうで大粒の雨が降り始めた。「あらあら、通り雨かねぇ」と背後からおばあちゃんの声が聞こえてくる。その景色をぼんやりと眺めているうちに、皆は会計を済ましてしまっていた。友達に声をかけられてその事に気付き、私もレジに向かう。お金を払うとおばあちゃんはゆっくりレジの下に手を伸ばし、私の手に何かを握らせた。手を開くと綺麗な包装紙に包まれた、真ん丸な飴玉がひとつ置かれていた。顔を上げるとおばあちゃんがにっこりと微笑んだ。私もつられて笑い返す。そうしている内に雨は上がっていた。その時私はある事を思いついた。帰る道すがら、友達に計画を話すと皆同意してくれた。そこで早速それを実行するために、その足で違う場所へ向かった。
駄菓子屋が閉店する日の午後六時前、私達は駄菓子屋のある通りからひとつずれた通りに集合した。建物の陰から駄菓子屋を覗くと、おばあちゃんが閉店の準備を始めようとしていた。今日はおばあちゃん一人ではなくお孫さんも一緒だった。六時になりおばあちゃんが辺りに人がいない事を確認すると、お店のシャッターを閉めようとした。その瞬間、私達はお店の前に飛び出した。
「おばあちゃん、今までありがとう!」
背後から聞こえてきたたくさんの声に、おばあちゃんとお孫さんが驚いて振り返る。そして私達は天高くあるものを投げた。
赤 青 黄 桃 橙 緑
色とりどりの袋に入った真ん丸な飴玉が空から降ってくる。
当たると痛いので人のいない場所に向かって投げたのだが、小学生達は喜んでその飴の下へ走っていく。おばあちゃんとお孫さんは目を飴玉のように真ん丸にして、その光景を見ていた。
「今までありがとう」
「雨の日に飴玉くれるの嬉しかった」
「お店がなくなるの寂しいよぅ」
小学生の子達が次々と声をかける。そしておばあちゃんに今までの感謝をつづった手紙を手渡した。
「皆、ありがとうね」
おばあちゃんは少し涙ぐみながら手紙を受け取り、一人一人にお礼を言っていく。
そして名残惜しそうに振り返りながら、お孫さんと共に帰っていった。
おばあちゃんが見えなくなった後、皆で飴玉を丁寧に拾っていった。拾い忘れがない事を確認すると一人二人と帰り始めた。拾った飴玉のひとつを、包装紙を外して口の中に入れた。そのヒビの入った飴玉からは、とても懐かしい味がした。
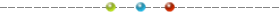
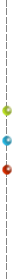
後書き 10.08.11.
授業で小説を書ける機会があって書いたものです。
言葉遊びをしてみたく、真っ先に思い浮かんだのが「雨」と「飴」でした。そうしたらこんな話が出来ました。
ちょっと展開が分かってしまうつくりになってしまわざるをえなかったのが残念です。
戻る